ギターにリバーブはいらない?必要性とおすすめを深堀り解説
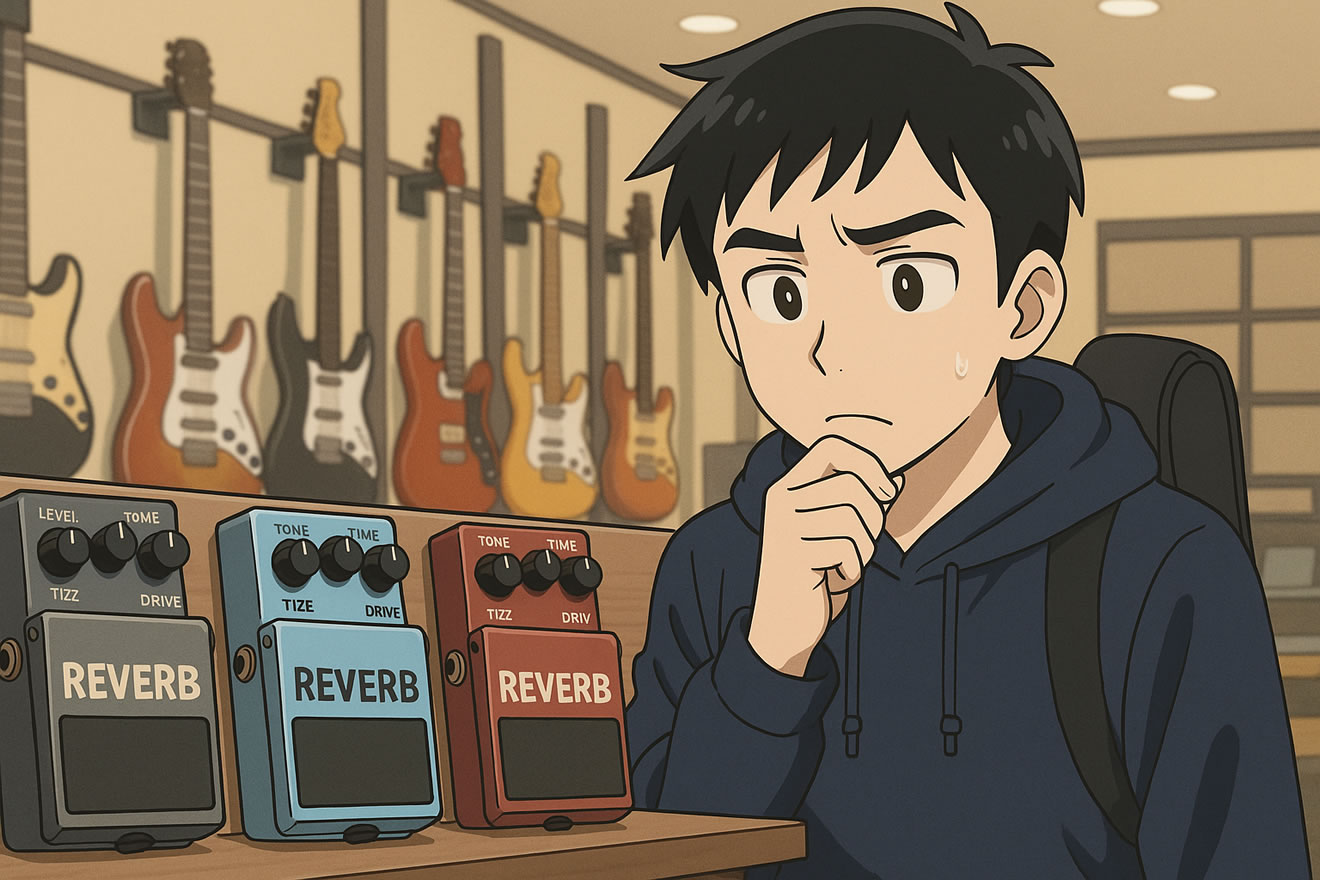
この記事はプロモーションが含まれます。
ギターの音作りにおいて「リバーブ」は定番のエフェクトのひとつですが、「リバーブはいらない」と言われることも少なくありません。
特に初心者にとっては、なぜそう言われるのか、その真意がわからず悩むポイントです。
ネットの情報を見て、「結局どうすればいいのか」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、リバーブの効果や特徴を分かりやすく解説したうえで、不要とされる理由についても客観的に紹介します。
実際の使用シーンに合わせたリバーブの活用法や、おすすめのエフェクター機種など、すぐに実践できる情報を網羅。
特に、リバーブに対して「使うべきか、使わないべきか」を迷っている層に向けて、丁寧に構成しています。
リバーブが本当に自分に必要なのかを判断したい方は、ぜひ本文をご覧ください。
おすすめ→おすすめのリバーブエフェクター5選
- リバーブの効果と特徴を正しく理解できる
- リバーブが不要とされる理由を知ることができる
- 自分に合ったリバーブの使い方を見極められる
- おすすめ機材や設定方法が具体的にわかる
ギターにリバーブはいらないのか考察

エレキギターを始めて少し経つと、音作りにも興味が出てきますよね。
そんな中で「リバーブって必要なの?」と疑問に思ったことはありませんか?
ここでは、リバーブの効果や不要だと感じる理由について、わかりやすく考えていきます。
- リバーブの効果と特徴
- ギターにリバーブはいらない人の意見
- ギターにリバーブを使うと下手になる?
- リバーブをかけっぱなしにするとどうなる?
- ディレイ/リバーブはどっちを先にかける?
リバーブの効果と特徴
リバーブは音に深みや広がりを加えるエフェクトです。
単なる飾りではなく、ギターサウンドの雰囲気や印象に大きく関わる要素です。
まずは、リバーブが持つ具体的な効果を知っておきましょう。
空間の広がりを演出する
リバーブは音に「残響」を加えることで、まるで大きなホールやスタジオで弾いているような空間の広がりを生み出します。
音が壁に反射して返ってくる感じを再現してくれるため、ギターの音が立体的に感じられるようになります。
これにより、演奏に包まれるような感覚が得られるのがリバーブの大きな魅力です。
音の輪郭を和らげる
リバーブをかけることで、ギターの音の「カド」が取れ、全体的に柔らかく聞こえるようになります。
特に歪んだ音やアタックが強めのサウンドでも、耳に刺さらず、聴きやすい印象に変わります。
音の粒がなめらかに繋がるため、自然で心地よい響きを作り出すことができます。
ノイズが目立たなくなる
ギターを弾くとき、どうしてもピッキングのブレや弦のノイズが出てしまいます。
リバーブを使うと、そのような細かいノイズやミスが音の中に自然に溶け込み、目立ちにくくなります。
これによって演奏全体がまとまり、少し粗くても「いい感じ」に聞こえることがあります。
音に余韻を加える
リバーブは音が消えた後にもふわっと残る「余韻」を加える効果があります。
これによって単音でも物足りなさがなく、感情を乗せた演奏がしやすくなります。
ソロやバラードでは特にその効果が大きく、音に表情を加えたいときに活躍します。
統一感やまとまりが生まれる
バンドや多重録音で複数の音が重なる場面では、リバーブが全体の音に統一感を与えてくれます。
個々の音がただ鳴っているのではなく、一体となって響いているように感じさせる効果があるのです。
自然なまとまりが生まれ、全体のバランスが整いやすくなります。
ギターにリバーブはいらない人の意見

リバーブの効果を知ると、使ってみたくなる気持ちは自然です。
しかし、一方で「リバーブはいらない」と考えるギタリストも少なくありません。
ここでは、リバーブを使わない派の意見をいくつか紹介します。
音がこもる
リバーブをかけすぎると、音が「もわっ」としてはっきりしなくなることがあります。
特に歪み系のエフェクターと合わせると、音の輪郭がぼやけやすくなります。
ギター本来の抜けの良さが失われるため、しっかりしたアタックやメリハリを大切にしたい人には不向きだと感じられることもあります。
演奏が聴き取りづらい
リバーブが強いと、ギターのフレーズ一音一音が埋もれて聴き取りにくくなる場合があります。
特に速いパッセージや細かいニュアンスを大事にしたいプレイでは、邪魔になることもあるでしょう。
音が響きすぎると、せっかくの表現が曖昧になってしまい、意図が伝わりにくくなることがあります。
ギターが上達しにくくなる
リバーブは音を美しく聴かせてくれますが、それゆえに「ごまかし」が効いてしまう側面もあります。
ピッキングのムラや音のミスも目立ちにくくなってしまうため、自分の演奏のクセに気づきにくくなる可能性があります。
練習段階ではなるべく素の音で演奏し、自分の技術と正面から向き合うことが大切だという意見もあります。
宅録やモニター環境では邪魔
自宅録音やスタジオモニター環境では、リバーブの細かな残響までクリアに聴こえます。
そのため、少しのかけすぎでも音が過剰に響いてしまい、全体のバランスを崩すことがあります。
録音した後にリバーブを加える方がコントロールしやすく、クリーンなミックスが可能だという考え方があります。
必要なときだけ後から足せばいい
リバーブは録音後やミキシング時に後から加えることができます。
そのため、最初からかけっぱなしにしておくよりも、必要な場面だけ使うという考え方もあります。
状況に応じて調整できるので、録音やライブでも柔軟に対応しやすくなります。
この意見は特に実践的な場面で重視されています。
ギターにリバーブを使うと下手になる?

「リバーブを使うと下手になる」と言われることがありますが、これは少し極端な表現です。
ただし、リバーブが演奏のアラやノイズをごまかしてくれる性質を持つのは事実です。
例えば、ピッキングの強弱や指の運びが甘くても、リバーブがかかっていれば音がなめらかにつながり、一見キレイに聴こえます。
しかし、それに慣れてしまうと、自分の弱点や演奏の粗さに気づきにくくなってしまいます。
結果として、技術の向上が遅れるという意味で「下手になる」という意見につながるのです。
特に初心者のうちは、できるだけリバーブを控えめにして、素の音での練習を重ねることが大切です。
音を飾らずに練習することで、指のコントロール力や耳の感覚が自然と育っていきます。
リバーブはあくまで「表現を補う道具」です。
基本的な演奏力を身につけたうえで使えば、むしろ演奏の魅力を引き立てる頼もしい味方になります。
リバーブをかけっぱなしにするとどうなる?

リバーブを常にオンにしていると、最初は気持ち良く感じられても、次第にその“ふわふわ感”が邪魔になることがあります。
特にバンド演奏や録音では、リバーブが他の楽器とぶつかって音が濁ったり、演奏の輪郭がぼやけてしまったりすることがあります。
また、部屋やスタジオなどの「実際の空間の響き」とリバーブの音が重なると、違和感が出やすくなります。
これにより、音が二重に聞こえたり、不要な反響が混ざってしまう場合もあるのです。
リバーブは「響き」を足すエフェクトなので、常に同じ設定で使い続けるのは避けたほうがよいでしょう。
演奏する場所や曲の雰囲気によって、適切な量やタイプを選ぶ意識が大切です。
リバーブをかけっぱなしにせず、「ここぞ」というときだけ使うことで、その効果を最大限に引き出すことができます。
ディレイ/リバーブはどっちを先にかける?

ディレイとリバーブの順番は、音作りに大きな影響を与えます。
基本的には「ディレイ → リバーブ」の順にかけるのが一般的です。
この順番だと、ディレイによって生まれた反復音にリバーブがかかり、自然な残響が加わることで空間的なまとまりが出ます。
まるでホールでディレイの反響が響いているような、リアルな音場が作れます。
逆に「リバーブ → ディレイ」の順にすると、残響のかかった音が繰り返されることになり、少し不自然に感じられる場合があります。
ただし、これはあくまでセオリーであって、逆の順番が悪いわけではありません。
エフェクトボードの中での配置や、自分が表現したいサウンドによって試してみる価値はあります。
大事なのは「なぜその順番にするのか」を自分の耳で確かめながら決めることです。
ギターにリバーブはいらない?賢い使い方

「リバーブは不要」と言われても、すべての場面に当てはまるとは限りません。
重要なのは、自分のプレイスタイルや環境に合わせて、リバーブを上手に使いこなすことです。
ここでは、リバーブが本当に必要かを見極めるヒントを紹介します。
- リバーブの必要性をチェック
- おすすめのリバーブエフェクター5選
- リバーブを使用した設定方法
- リバーブをかけるときの注意点
- 音作りでリバーブをかけすぎていた話
リバーブの必要性をチェック
リバーブを使うかどうか迷ったときは、自分のサウンドに何が足りないかを考えてみましょう。
以下のようなポイントに当てはまるなら、リバーブがあなたの演奏を一段上に引き上げてくれるかもしれません。
音がスカスカに感じることがある
ギターの音が「なんとなく薄い」と感じたことがあるなら、リバーブを加えることで厚みを持たせられます。
残響を加えることで空間に広がりが出て、音が豊かに響くようになります。
単体では物足りなさを感じるとき、リバーブは非常に頼れる存在です。
ソロやアルペジオをよく弾く
単音で構成されるソロやアルペジオは、音と音の間に「間」が生まれます。
この間をリバーブで埋めてあげることで、より滑らかで感情的な演奏に仕上がります。
音の余韻が加わることで、聴いている人の心にも響きやすくなります。
ライブで他の音に埋もれがち
バンド演奏やライブでは、ギターの音が他の楽器に埋もれてしまうこともあります。
その場合、適度にリバーブを加えることで音が立体的になり、埋もれにくくなることがあります。
存在感を引き出すための工夫として、リバーブは有効な手段の一つです。
理想の音に残響が含まれている
自分が「かっこいい」と思う音に、ふんわりとした残響が含まれているなら、それはリバーブの力かもしれません。
プロの音源やライブ映像を聴いて、「この音が出したい」と感じたら、似た響きを意識してみましょう。
音の質感を真似るところから、自分らしいサウンドメイクが始まります。
好きなギタリストが使用している
憧れのギタリストがリバーブを使っているなら、それを試してみる価値は十分にあります。
同じ機材や設定に近づけることで、音作りの方向性が見えてくることもあります。
自分のルーツをたどるような感覚で、リバーブの使い方を研究してみましょう。
おすすめのリバーブエフェクター5選

リバーブの使用を検討している方に向けて、初心者でも扱いやすく、かつ高品質なリバーブエフェクターを5つご紹介します。
それぞれ異なる特徴を持っており、あなたの音作りに新たな可能性をもたらしてくれるでしょう。
BOSS / RV-6
BOSSのRV-6は、コンパクトながら8種類のリバーブモードを搭載した多機能ペダルです。
Room、Hall、Plateなどの定番から、ModulateやShimmerといった現代的なモードまで幅広く対応しています。
Dynamicモードでは、演奏の強弱に応じてリバーブの深さが自動調整され、自然な響きを実現します。
シンプルな操作性と高い音質で、初心者からプロまで幅広く支持されています。
Electro-Harmonix / Holy Grail Nano
Holy Grail Nanoは、シンプルな操作性と高品質なリバーブサウンドが魅力のペダルです。
Spring、Hall、Flerbの3種類のリバーブモードを搭載しており、特にSpringリバーブはクラシックなアンプの響きを再現しています。
Flerbモードでは、フランジャーとリバーブを組み合わせた独特の空間効果を得ることができます。
コンパクトなサイズで、ペダルボードにも無理なく組み込めます。
TC Electronic / Hall of Fame 2
Hall of Fame 2は、多彩なリバーブサウンドとカスタマイズ性を兼ね備えたペダルです。
新たに追加されたShimmerリバーブは、オクターブ上の音を加えることで幻想的な響きを演出します。
MASH機能により、ペダルを踏み込む強さでエフェクトの深さをコントロール可能です。
また、TonePrint機能を使えば、スマートフォンアプリから好みの設定をダウンロードして適用できます。
MXR / M300 Reverb
MXRのM300 Reverbは、6種類の高品質なリバーブモードを搭載したペダルです。
Plate、Spring、Epic、Mod、Room、Padといった多彩なモードが用意されており、各モードはMXRのデザインチームによって丁寧に調整されています。
Constant Headroom Technology™により、20ボルトのヘッドルームを確保し、クリアでダイナミックなサウンドを実現しています。
シンプルな3ノブ設計で、直感的な操作が可能です。
Walrus Audio / Slö
Slöは、アンビエントやドリーミーなサウンドを求めるギタリストに最適なリバーブペダルです。
Dark(低音オクターブ)、Rise(アンビエントスウェル)、Dream(ラッチングパッド)の3つのモードを搭載し、それぞれ独自のテクスチャーを持っています。
さらに、リバーブトレイルのモジュレーション波形を切り替えることで、より多彩な表現が可能です。
独創的なサウンドメイクを追求する方におすすめの一台です。
リバーブを使用した設定方法

リバーブは「ただかければいい」ものではなく、演奏する曲調や場面に応じて使い分けることが大切です。
ここでは、具体的なシチュエーションごとにおすすめの設定方法をご紹介します。
自分の理想の音に近づけるヒントとして参考にしてください。
自宅練習・自然な空間感を出したいとき
自宅で練習するときは、音が乾いて聞こえがちで、長時間のプレイで耳が疲れやすくなることもあります。
そこで、RoomやHallなどの控えめなリバーブをかけることで、演奏に自然な空間の広がりを加えることができます。
Mix(ミックス)設定は20~30%程度、Decay(残響の長さ)は短めにして、演奏を邪魔しない程度に留めましょう。
これにより、実際に部屋で鳴っているような自然な響きを再現できます。
ソロやバラードで感情を出したいとき
エモーショナルな演奏をするときは、音に余韻があることで感情の波が伝わりやすくなります。
HallやPlateリバーブがおすすめで、Decayはやや長め、Mixは40〜50%を目安に設定してみましょう。
演奏の後に残る「余韻」が、聴く人の心に印象を残す重要な要素になります。
ただし、かけすぎると輪郭がぼやけるので、バランスは丁寧に調整してください。
アンビエント・浮遊感重視のとき
音に「浮遊感」や「幻想的な雰囲気」を求める場合は、ShimmerやModリバーブのような個性的なモードを活用しましょう。
Decayは長めに設定し、Mixも50%以上にすることで、空間に溶け込むようなサウンドが得られます。
ピッキング音よりも残響がメインになるイメージで、あえてアタック感を控えめにすることで世界観が際立ちます。
アンビエントミュージックやソロプレイにおすすめの使い方です。
リバーブをかけるときの注意点

リバーブは便利で感情豊かなサウンドを作り出せる反面、使い方を間違えると音の輪郭が失われたり、他の楽器とぶつかったりすることがあります。
ここでは、リバーブを使う上で気をつけたい5つのポイントを紹介します。
失敗を防ぎつつ、自分らしい音作りを目指しましょう。
かけすぎに注意
リバーブを強くかけすぎると、演奏の細かいニュアンスがぼやけてしまいます。
特に速いフレーズや複雑なコード進行では、音が混ざって聴き取りにくくなりがちです。
適切な量のリバーブは音に深みを与えますが、多すぎると逆効果になります。
まずは控えめにかけて、少しずつ調整するのがコツです。
演奏場所に合わせる
リバーブの効果は、演奏する場所の音響にも大きく影響されます。
例えば、ライブハウスのように残響が多い場所では、リバーブを強くかけると音がにごってしまうことがあります。
逆にデッドな部屋での演奏では、ある程度リバーブを加えることで自然な広がりが生まれます。
環境に応じて設定を変えることが大切です。
ジャンルに合った使い方を
リバーブのかけ方は、演奏するジャンルによって向き不向きがあります。
たとえば、メタルやパンクなどアタックが重要なジャンルでは、リバーブが強すぎると勢いが失われることがあります。
逆に、ジャズやアンビエントなどでは深めのリバーブが雰囲気作りに効果的です。
ジャンルの特性を理解したうえで、音作りを工夫しましょう。
録音時のかけ録りは慎重に
録音の際にリバーブを「かけ録り」すると、あとで編集が難しくなる可能性があります。
ミックスの段階でリバーブを調整できるように、「かけ録り」は必要最低限にするのがおすすめです。
一度かけてしまうと取り除けないため、後悔しないためにもドライな音(リバーブなし)でも録っておくと安心です。
特に宅録では、柔軟な編集のために慎重な判断が求められます。
他のエフェクトとのバランス
リバーブは単独で使うことも多いですが、ディレイやコーラスなど他のエフェクトと組み合わせる場面もあります。
その際、各エフェクトの役割や順番を理解しておかないと、音がごちゃごちゃになってしまいます。
特にディレイとのバランスは難しく、どちらか一方が強くなりすぎないよう注意が必要です。
エフェクト同士の「引き算」も大切なテクニックです。
音作りでリバーブをかけすぎていた話

筆者がギターを始めて1年ほど経った頃、BOSSのGT-5というマルチエフェクターを使い始めました。
幻想的なクリーントーンを目指し、きらびやかで透明感のある音に憧れていたんです。
その中で「リバーブを深くかけるとプロっぽい音になる」と思い込み、Hall系リバーブを強めに設定していました。
最初は「広がりがあって気持ちいい!」と満足していたのですが、録音してみると音がぼやけていて、フレーズがはっきり聞こえないことに気づきました。
また、スタジオで他の楽器と合わせると、自分のギターだけ埋もれてしまって存在感がなくなってしまったんです。
そこからようやく、リバーブは「足す」ものではなく「整える」ものだと実感しました。
今では必要に応じて控えめに使うようにし、場面ごとに設定を見直すことの大切さを感じています。
ギターにリバーブはいらないの総括
記事のポイントをまとめます。
- リバーブは音に広がりや深みを加える空間系エフェクト
- リバーブを使いすぎると音がこもって聴き取りづらくなる
- 上達のためにはリバーブを控えめにして演奏の粗を確認する
- 宅録やモニター環境ではリバーブが邪魔になることがある
- 必要なときだけ後からリバーブを加える方法もある
- リバーブは状況に応じて適切に調整することが重要
- 音がスカスカに感じるときはリバーブが効果的
- ソロやアルペジオではリバーブで表現力が高まる
- 他の楽器に埋もれる場面ではリバーブを工夫する
- かけすぎを避けて他のエフェクトとのバランスを取る


