ヤマハFGは弾きにくい?その原因と解決方法を徹底解説
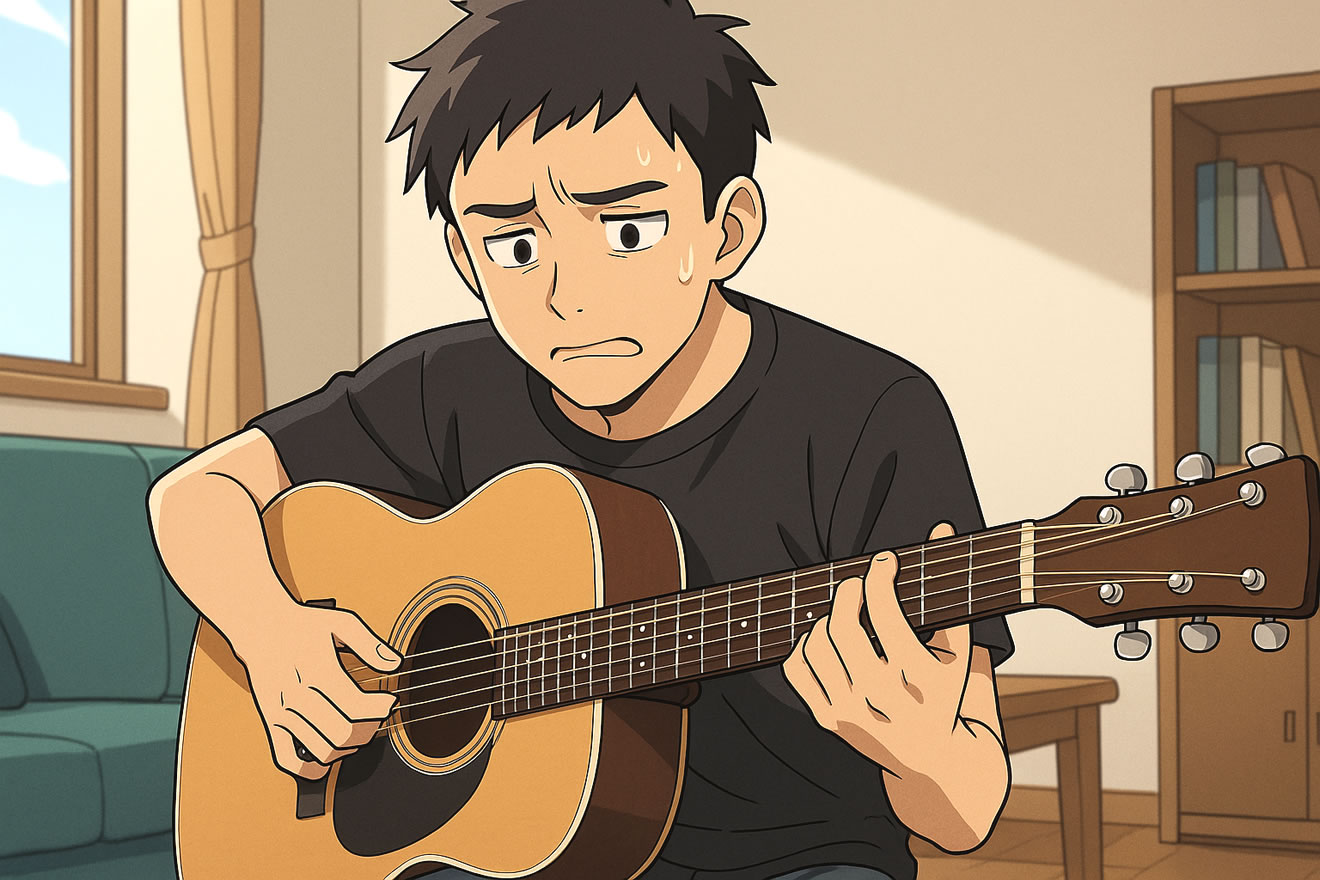
この記事はプロモーションが含まれます。
ヤマハのFGシリーズに興味があるけれど、「弾きにくい」という評判を見て不安に感じたことはありませんか?
ネット上にはさまざまな意見があり、ネガティブな意見を見て迷ってしまう方も少なくありません。
本記事では、FGシリーズが「弾きにくい」と言われる理由を丁寧に紐解きながら、特徴や選び方、さらに弾きやすくする具体的な方法をご紹介します。
読み進めていただくことで、FGシリーズの本当の魅力や、自分に合った一台を選ぶためのヒントがきっと見つかります。
初心者から中級者まで、幅広いプレイヤーが安心して選べるFGシリーズ。
その性能を最大限に活かすためには、弦高やネック調整といった基本的な知識と、少しの工夫が必要です。
「自分にとって本当に弾きやすいギターとは何か」を知るために、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
おすすめ→ヤマハFGシリーズのおすすめギター5選
- ヤマハFGの弾きにくさの原因と対処法が具体的に分かる
- 自分に合ったFGシリーズのモデル選びのポイントが理解できる
- 中古購入時に注意すべきチェックポイントが把握できる
- 実際の試奏体験からFGの魅力や使いやすさがイメージできる
ヤマハのFGは弾きにくいのか考察

ヤマハのFGシリーズについて調べていると、「弾きにくい」という意見を目にすることがあります。
しかし、その評価には様々な背景があり、簡単には決めつけられませんん。
まずはFGシリーズの特徴を整理し、本当に弾きにくいのかを多角的に考察していきましょう。
- ヤマハFGの特徴
- FGが弾きにくいと言われる理由
- ヤマハFG/FSの主な違い
- ヤマハFG830の評価を調査
- YAMAHA FGシリーズの歴史は?
- ヤマハのFS820とFS830はどっちがいい?
- ヤマハFGを使っているアーティストは?
ヤマハFGの特徴
ヤマハFGシリーズは、多くのギタリストから長年支持されてきた定番のアコースティックギターです。
では、具体的にどのような魅力があるのでしょうか?
ここでは、FGシリーズが評価される主な理由を5つのポイントに分けてご紹介します。
音のバランスが良い
ヤマハFGシリーズは、低音から高音までバランスの取れたサウンドが特徴です。
単音で弾いてもコードで鳴らしても、どの音域もクリアに響くため、ジャンルを問わず使いやすいと感じる方が多いです。
特にストローク時の音のまとまりが良く、アンサンブルの中でも埋もれにくい存在感を放ちます。
この音の均整が、演奏者の表現をしっかり支えてくれるのです。
初心者でも使いやすい
FGシリーズは、初心者にも扱いやすいギターとしても知られています。
ネックが太すぎず細すぎず、手の小さい方でも押さえやすい仕様です。
また、弾いたときのレスポンスが良く、初めてのコードでも音が出しやすい工夫がなされています。
初学者の「弾けた!」という喜びを支える、優しい設計が詰まっているのがこのシリーズの魅力です。
しっかりした作りで長持ち
ヤマハFGは、価格帯を超えるほどしっかりとした作りで評価されています。
木材の選定から加工、仕上げに至るまで、丁寧な製造工程が信頼感を生み出しています。
そのため、長年弾き続けてもボディやネックの変形が少なく、メンテナンスさえすれば長く付き合える一本です。
品質の高さが、初心者から中級者、さらには上級者にも支持されている理由の一つです。
手が届きやすい価格帯
ヤマハFGシリーズは、クオリティの高さに対して価格が非常にリーズナブルです。
入門用としても購入しやすく、それでいて安価な印象を与えない音質とデザインを持っています。
「価格以上の満足感が得られるギター」として、多くのユーザーがコストパフォーマンスの高さを評価しています。
学生や若い社会人にとっても手が届きやすい点は大きな魅力です。
見た目がシンプルで飽きない
FGシリーズは装飾が控えめで、ナチュラルな木目や落ち着いたカラーリングが特徴です。
このシンプルさが逆に洗練された印象を与え、長く使っていても飽きがきません。
派手すぎないデザインは、どんなシーンでも自然に馴染み、自分らしいスタイルで演奏を楽しめます。
見た目の美しさと実用性のバランスも、このシリーズの大きな魅力と言えるでしょう。
FGが弾きにくいと言われる理由

ヤマハFGシリーズには高評価が多くありますが、一方で「弾きにくい」と感じる方の声も存在します。
これはギターそのものの問題というより、使う人の環境や状況によるケースが多いです。
ここでは、弾きにくさを感じる主な理由を5つに分けて解説します。
弦高が高すぎる
「弦高(げんこう)」とは、弦と指板の間の高さを指します。
この弦高が高いと、指で弦を押さえるのに力が必要になり、コードを綺麗に鳴らすのが難しくなります。
ヤマハFGシリーズは、出荷時にやや高めの弦高で設定されていることが多く、そのまま弾くと指が疲れやすく感じる方もいます。
しかし、弦高は後から調整可能です。
ギターショップでセッティングをお願いすれば、自分に合った高さに整えてもらうことができます。
ネックの反りや調整不足
ギターのネックが反っていると、特定のフレットで音が詰まったり、逆に弦高が高くなってしまうことがあります。
これは湿度や温度変化、長期間の保管状態によって自然に起こることもあります。
ヤマハFGに限らず、どんなギターでもネックの状態は定期的に確認が必要です。
反りが原因で弾きにくいと感じたら、トラスロッドという部分を調整することで改善されます。
初心者の場合は、無理に自分で直そうとせず、楽器店に相談するのが安心です。
弦のゲージが合っていない
弦の太さ(ゲージ)が自分の指に合っていない場合も、弾きにくさの原因になります。
ヤマハFGは標準でやや太めの弦が張られていることが多く、初心者には指が痛く感じることがあります。
特に、まだ指が慣れていない時期は、ライトゲージやエクストラライトと呼ばれる柔らかい弦に交換するだけで、格段に弾きやすくなります。
弦の種類を見直すことで、演奏のストレスが大きく軽減されるでしょう。
ボディのサイズが大きすぎる
ヤマハFGシリーズは「ドレッドノート」と呼ばれるボディ形状を採用しています。
これは大きくて深みのある音を出す反面、体格が小さい人にとっては構えづらく感じることもあります。
腕をまわしにくい、肩が疲れる、姿勢が安定しないといった理由から、「弾きにくい」と感じてしまうケースがあります。
この場合は、ヤマハのFSシリーズのような少し小ぶりなモデルを選ぶと、体へのフィット感が良くなり、快適に演奏できます。
演奏技術が未熟な問題
弾きにくさの原因が、実はギターではなく自分の演奏技術にあることも少なくありません。
コードチェンジの遅さや、押さえ方の癖、指の力加減などによって「音が出にくい」と感じる場合があります。
これは決して恥ずかしいことではなく、誰もが通る道です。
むしろ、こうした違和感を通じて「どうすれば弾きやすくなるか」を学ぶことが、上達への近道になります。
正しいフォームや練習法を意識することで、ギターの印象もガラッと変わってくるはずです。
ヤマハFG/FSの主な違い
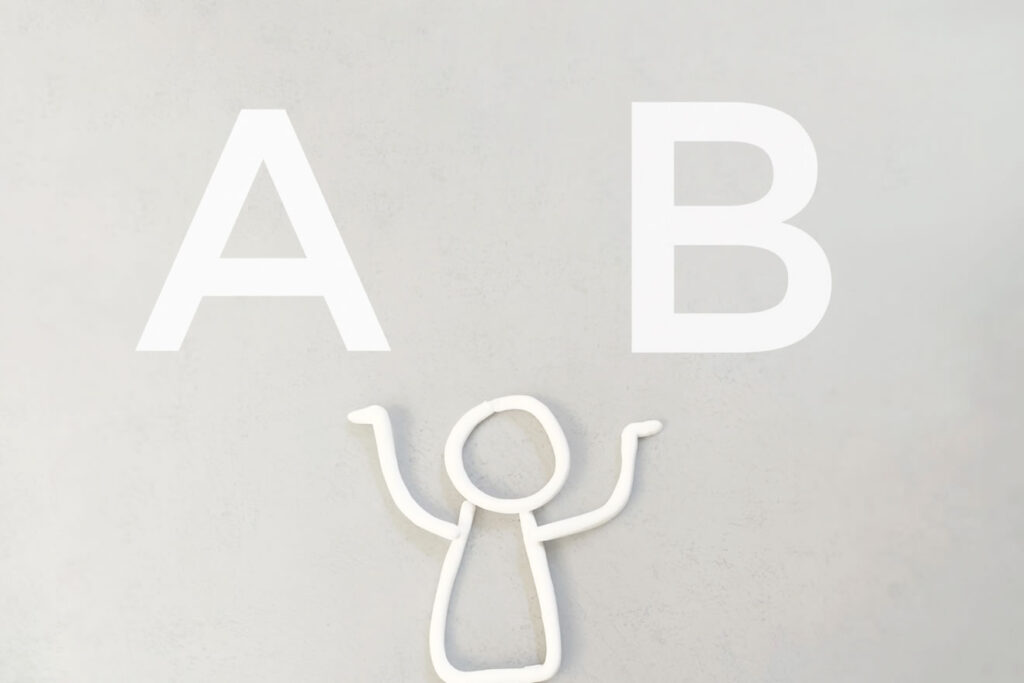
ヤマハのアコースティックギターシリーズであるFGとFSは、見た目こそ似ていても、それぞれ異なる個性を持っています。
どちらを選ぶべきか悩んでいる方に向けて、両モデルの違いを項目別に分かりやすくご紹介します。
ボディのサイズと形状
FGシリーズは「ドレッドノート型」と呼ばれる大きめのボディを採用しています。
そのため、重厚感があり、見た目にも存在感があります。
一方、FSシリーズは「コンパクト・フォーク型」とも言われ、小柄で抱えやすいサイズです。
特に体格が小さめの方や女性、子どもにも扱いやすく、構えたときのフィット感が良好です。
体への負担を減らしたい人には、FSの方が適しているかもしれません。
音の特性
FGは低音から高音までの音域が広く、特に中低音に厚みがあるのが特徴です。
ストロークでガツンと音を出すスタイルに向いていて、バンド演奏でも音に埋もれにくいです。
一方、FSは高音域がクリアで繊細な響きがあり、フィンガーピッキングやソロ演奏にぴったりです。
音のキラキラ感や輪郭の鮮明さを求める方には、FSが好まれます。
プレイ感
FGはそのサイズゆえに構え方に慣れが必要で、初心者の方には少し大きく感じることもあります。
逆に、FSは体への密着感があり、軽量で操作性に優れています。
演奏中に腕が疲れにくく、細かい指の動きもしやすいので、練習時のストレスも少なく済みます。
特に長時間の練習やライブで持ち続ける場合には、FSのプレイアビリティの良さが際立ちます。
使用シーン
FGはストローク中心のプレイや弾き語り、屋外での演奏など、大きな音量が求められる場面に適しています。
音の厚みがあるため、広い場所でもしっかりと音が届きます。
FSは自宅練習やレコーディング、アコースティックライブなど、繊細な表現を重視するシーンにぴったりです。
周囲に配慮が必要な環境でも、扱いやすい音量とバランスを発揮します。
外観とデザイン
FGとFSはどちらも木材の美しさが活かされたシンプルなデザインが魅力ですが、ボディサイズが異なることで印象も変わってきます。
FGは力強く、どっしりとした印象で、クラシックなアコギの風格があります。
一方、FSはすっきりとしたスマートな見た目で、洗練された雰囲気を感じさせます。
持ち主の好みや演奏スタイルに応じて、どちらも魅力的な選択肢となるでしょう。
どちらも良さがある
ヤマハFGは迫力のあるサウンドと堂々としたサイズ感が特徴で、ストロークに向いています。
一方、FSはコンパクトで扱いやすく、繊細なプレイを得意とするモデルです。
どちらが良いかは、体格や演奏スタイル、求める音によって変わってきます。
自分の目的に合ったモデルを選ぶことで、ギターライフがさらに楽しいものになるでしょう。
ヤマハFG830の評価を調査

ヤマハFG830は、ヤマハFGシリーズの中でも特に人気の高いモデルです。
実際に使用しているユーザーからの口コミやレビューをもとに、良い評価と辛口評価の両面からその魅力と課題を探っていきます。
良い評価
ヤマハFG830は、多くのユーザーから「コストパフォーマンスが抜群」と高く評価されています。
特に、サイドとバックにローズウッドを使用している点が、音の深みや広がりを生んでおり、この価格帯でここまで豊かなサウンドを出せるのは驚きとの声が多く見られます。
ストローク時の音圧がしっかりしていて、弾き語りにもぴったり。
さらに、外観の美しさも魅力のひとつで、光沢のある仕上げや木目の上品さに惹かれる方も少なくありません。
初心者だけでなく、中級者やセカンドギターを探している人からも支持されており、長く愛用できるモデルとして親しまれています。
価格を超える満足感を得られる1本として、多くの高評価レビューが寄せられています。
辛口評価
一方で、ヤマハFG830に対しては「最初の状態だと弾きにくさを感じた」という意見もあります。
特に、出荷時に設定されている弦高がやや高めで、指が疲れやすいと感じる人も少なくありません。
また、弦のゲージが標準仕様のため、初心者にとってはやや硬く感じられることもあり、「最初の一本としてはちょっと厳しいかも」といった声も見受けられます。
音に関しては、「高音が少し強すぎて耳に刺さる感じがある」といった意見も一部あります。
これはプレイスタイルや好みにもよりますが、繊細なニュアンスを重視する方にとっては、少し主張が強く感じられることがあるようです。
このような点は、セッティングの調整や弦交換である程度カバーできますが、購入後の一工夫が求められるモデルとも言えます。
YAMAHA FGシリーズの歴史は?

ヤマハのFGシリーズは、1966年に初代モデル「FG180」が登場して以来、長い歴史を持つアコースティックギターの代表的シリーズです。
「FG」は“Folk Guitar”の略で、当初から日本国内外のフォークシンガーや弾き語りアーティストたちに愛されてきました。
その理由の一つは、手頃な価格でありながらしっかりとした作りと安定したサウンドを実現していた点です。
年月を重ねるごとに改良が加えられ、2000年代には音響解析技術「A.R.E(Acoustic Resonance Enhancement)」などの新技術も導入。
2020年代に入ってもなお、初心者からプロまで幅広く支持され続けています。
FGシリーズは、ただのギターではなく、時代を超えて受け継がれてきたヤマハのものづくり精神を体現するモデルです。
その歴史を知ることで、FGがなぜ多くの人に選ばれるのかがより深く理解できるでしょう。
ヤマハのFS820とFS830はどっちがいい?

ヤマハFSシリーズの中でも、FS820とFS830は人気の高い2モデルです。
どちらも同じサイズ感でプレイアビリティはほぼ同じですが、使用している木材の違いが音のキャラクターに影響しています。
FS820はサイドとバックにマホガニーを採用しており、柔らかく温かみのある音が特徴です。
コードを弾いたときにまとまりがよく、ボーカルの邪魔をしない音色なので、弾き語りとの相性が良好です。
一方、FS830はローズウッドを使用しており、低音から高音まで幅広い音域を持ち、音の輪郭がはっきりしています。
ソロ演奏やフィンガーピッキングなど、繊細なニュアンスを表現したい人に向いています。
最終的には、どんな音を求めるかが選択のポイントです。
温かく優しい音が好みならFS820、クリアで広がりのある音を求めるならFS830がおすすめです。
ヤマハFGを使っているアーティストは?

ヤマハFGシリーズは、プロ・アマ問わず多くのアーティストに愛用されてきました。
その理由は、音の安定感と耐久性、そして演奏のしやすさにあります。
たとえば、あいみょんさんは自身のインタビューで、ヤマハFGを練習用ギターとして使っていたことを語っています。
また、押尾コータローさんのようなフィンガースタイルの名手も、ヤマハのアコースティックギターに信頼を置いており、ライブやレコーディングで使用しています。
海外ではエリック・クラプトンやボブ・ディランといった伝説的なアーティストたちも、かつてヤマハのギターを使用した実績があります。
もちろん、彼らはハイエンドモデルを使うことも多いですが、FGシリーズのようなスタンダードモデルも、彼らの音楽活動の一部を支えてきました。
プロも認めるギターという点で、FGは初心者にも自信を持っておすすめできる一本です。
ヤマハのFGは弾きにくいときの解決策

「ヤマハFGは弾きにくい」と感じたとしても、すぐにギター選びに後悔する必要はありません。
少しの工夫や調整で、格段に弾きやすくなる可能性があります。
ここでは、FGシリーズ特有の弾きにくさを解消するための具体的な対処法をご紹介します。
- FGの弾きにくさを解消するコツ
- ヤマハFGシリーズのおすすめギター5選
- ヤマハFG830の中古を買うポイント
- ヤマハのFGの試奏体験談
FGの弾きにくさを解消するコツ
ギターの弾きにくさは、必ずしも製品の問題だけとは限りません。
自分の体格やプレイスタイル、経験値に合った調整を施すことで、見違えるほど快適な演奏感が得られることもあります。
以下のポイントを押さえることで、FGシリーズをより自分にフィットさせることができます。
弦高を調整する
ギターが弾きにくいと感じたとき、まず見直したいのが弦高の設定です。
もしコードを押さえる際に指が疲れやすかったり、音がうまく鳴らなかったりする場合は、弦高が高すぎる可能性があります。
そうした場合は、自分でサドルやトラスロッドを調整するか、専門店でセッティングを依頼するのが安心です。
個人差はありますが、初級者にはやや低めの弦高が扱いやすいとされています。
理想的な高さに調整することで、弾きやすさが大きく向上し、演奏のストレスがぐっと減るはずです。
ネックの反りを調整
ギターのネックが反っていると、特定のポジションで音が詰まったり、逆に弦高が高くなって弾きづらく感じることがあります。
ネックの反りは気温や湿度によっても変化するため、季節によって調整が必要になることも。
「ネックがまっすぐかどうか」は、プロにチェックしてもらうのが確実です。
楽器店でトラスロッドという棒を使って微調整してもらうことで、弾きやすさが大きく向上します。
柔らかい弦に交換
ヤマハFGに初期搭載されている弦は、標準的なミディアムライトゲージで、初心者にはやや硬く感じられることがあります。
指が痛くなったり、押さえるのが難しいと感じるなら、ライトゲージやエクストラライトといった柔らかい弦に交換してみましょう。
弦を変えるだけで、押さえやすさと疲れにくさが改善され、演奏の楽しさが増します。
ただし、弦の種類によって音のニュアンスも変わるので、自分の好みに合ったものを選ぶのが大切です。
指の使い方を見直す
弦の押さえ方や指の角度が原因で「弾きにくい」と感じているケースも少なくありません。
特に初心者のうちは、無理な力を入れて押さえたり、指が寝すぎて隣の弦に触れてしまうなどの問題が起こりがちです。
まずはリラックスした姿勢で、正しいフォームを意識してみましょう。
YouTubeの演奏動画や教則サイトを参考に、指の使い方を見直すだけでも驚くほど弾きやすくなります。
ストラップの長さを調整
立って演奏する場合、ストラップの長さも弾きやすさに大きく影響します。
ストラップが長すぎるとギターの位置が下がりすぎて、ネックを持ち上げる力が必要になったり、コードが押さえにくくなることがあります。
逆に短すぎても腕が窮屈になり、演奏に支障が出ることがあります。
自分の自然な姿勢で、ネックやボディが安定する長さに調整してみましょう。
快適なポジションが見つかれば、演奏もスムーズに感じられるようになります。
ヤマハFGシリーズのおすすめギター5選

ヤマハFGシリーズは、初心者から上級者まで幅広い層に支持されるアコースティックギターの定番です。
各モデルにはそれぞれの特徴があり、音質やデザイン、価格帯などが異なります。
ここでは、特に人気のある5つのモデルをご紹介します。
FG830
FG830は、トップ材にスプルース単板、サイドとバックにローズウッドを採用したモデルです。
ローズウッドの特性により、明瞭で芯のあるサウンドと豊かなサスティンが特徴です。
また、ヤマハ独自のスキャロップドブレイシングが低音域の響きを強化し、バランスの取れた音色を実現しています。
価格以上の音質と演奏性を持ち、コストパフォーマンスに優れた一本です。
FG800
FG800は、ヤマハFGシリーズのエントリーモデルとして位置づけられています。
トップ材にスプルース単板、サイドとバックにナトーまたはオクメを使用し、明るくクリアな音色が特徴です。
新開発のスキャロップドブレイシングにより、レスポンスの良さと力強いサウンドを実現しています。
シンプルで伝統的なデザインと手頃な価格で、初心者にもおすすめのモデルです。
FG820
FG820は、トップ材にスプルース単板、サイドとバックにマホガニーを採用したモデルです。
マホガニーの特性により、温かみのある中低域が強調された音色が特徴です。
また、ヤマハ独自のスキャロップドブレイシングが低音域の鳴りを強化し、豊かな響きを実現しています。
豊富なカラーバリエーションも魅力で、初心者から中級者まで幅広く対応できるモデルです。
FG850
FG850は、表板、裏板、側板すべてにマホガニーを使用したモデルです。
マホガニーの特性により、豊かな中音域と温かみのある音色が特徴です。
ボディバインディングにもマホガニーを施し、木のぬくもりを感じさせるデザインに仕上げられています。
個性的な外観とサウンド特性が絶妙に調和し、演奏者の個性を引き立てる一本です。
FG5
FG5は、ヤマハのRed Labelシリーズの上位機種で、日本国内で製作されたモデルです。
トップ材にA.R.E.処理を施したシトカスプルース単板、サイドとバックにマホガニー単板を採用し、長年弾き込まれたような豊かな鳴りが特徴です。
オリジナルジャンボボディシェイプと新開発のスキャロップドブレイシングにより、深みのある低音と豊かな倍音を実現しています。
高品質な素材と熟練した技術者による製作で、プロフェッショナルな演奏にも対応できる一本です。
ヤマハFG830の中古を買うポイント

ヤマハFG830は新品でも人気の高いモデルですが、中古市場にも多く出回っており、お得に手に入れられるチャンスがあります。
しかし、中古品は状態に差があるため、事前のチェックがとても大切です。
ここでは、FG830を中古で購入する際に見ておくべきポイントをご紹介します。
傷や凹みを確認
中古ギターでは、外装の状態を丁寧に確認することが重要です。
特に、ボディの表面やエッジ部分には目立たない小さな傷や打痕があることがあります。
演奏に支障がなければ問題ありませんが、気になるようなら購入前にしっかりチェックしましょう。
できれば現物を直接見て、手で触れて確認するのがおすすめです。
ネックの反り具合を確認
ネックの状態はギターの弾きやすさに直結します。
特に中古品では、長年の使用によってネックが順反りや逆反りしている場合があります。
軽い反りであればトラスロッドで調整できますが、大きな変形があると修理が必要になることも。
購入前にネックの真っ直ぐさをチェックし、できれば専門店に見てもらうのが安心です。
フレットの状態を確認
フレットの減り具合も要チェックポイントです。
フレットが大きくすり減っていると、音詰まりやチューニングの不安定さが発生することがあります。
特に1〜5フレットあたりはコードをよく押さえる部分なので、減りが進んでいることが多いです。
状態が悪いとリフレット作業が必要になり、思わぬ出費につながる可能性もあるので注意しましょう。
音の鳴りをチェック
実際に音を出してみることで、そのギターの個性やクセが分かります。
ボディにクラックがあると、音がこもったり、鳴りが悪くなっていることがあります。
また、各弦の音量バランスやサスティンの具合も確認しておくと安心です。
弾いてみて「気持ちよく響くか」を基準に選ぶのがポイントです。
価格とのバランスを考える
中古ギターは、状態と価格のバランスが大切です。
相場より極端に安いものは、何らかの不具合がある可能性があります。
逆に高額すぎる場合は、新品購入も視野に入れて比較検討するのが賢明です。
総合的に見て、自分にとって納得できる条件であれば、中古でも良い買い物になります。
ヤマハのFGの試奏体験談

筆者は先日、都内の楽器店でヤマハFG830を試奏する機会がありました。
以前からFGシリーズには興味がありましたが、口コミで「弾きにくい」との声もあったため、正直少し不安も抱えていました。
実際に手に取ってみると、第一印象は「しっかりした作りだな」というものでした。
やや太めのネックは、最初は少し構えにくいと感じましたが、慣れてくると安定感があり、コードを押さえるのにも安心感がありました。
音は非常にバランスが良く、特にローズウッド特有の低音の深みが心地よく響き、指弾きでもストロークでも気持ちよく鳴ってくれます。
ただ、普段エレキギターを使用しているため、アコースティックギターは弾きづらい印象がありました。
これはヤマハのFGに限ったことではありませんが、アコギに慣れていない人は特にそう思うのかもしれません。
それを店員さんに伝えたところ、調整でかなり変わるとのこと。
総じて、筆者にとってFG830は「扱いやすさ」と「音の良さ」を両立したギターだと感じました。
ヤマハのFGは弾きにくいの総括
記事のポイントをまとめます。
- ヤマハFGは音のバランスが良く、初心者にも扱いやすい
- 弦高が高めで弾きにくさを感じることがあるが調整可能
- ネックの反りや弦の太さによっても演奏性が変わる
- FGとFSはボディサイズや音質、演奏感に明確な違いがある
- FG830は音の厚みと低音の響きが魅力で評価が高い
- 中古購入時はネックやフレットの状態を丁寧に確認すべき
- 弾きにくさの解消には、弦高やストラップの調整が効果的
- 柔らかい弦に交換することで押さえやすさが向上する
- FGシリーズはデザインもシンプルで長く愛用しやすい
- アーティスト使用例や歴史からもシリーズの信頼性が分かる


